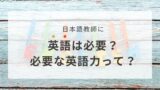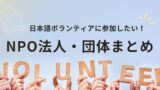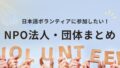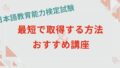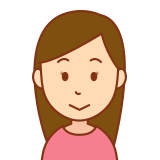
やさしい日本語はどんなもの?
実際にどんな場面で使われている?
このように、やさしい日本語をよく知らないという方も多いと思います。
本記事はやさしい日本語について理解を深めたい方が対象です。
やさしい日本語が作られた背景や自治体の取り組みなどを中心に解説していきます。
やさしい日本語の作り方についてもお話していきますのでぜひ最後までお読みください。
やさしい日本語とは?

「やさしい日本語」という言葉を初めて聞いたという方も多いかもしれません。
やさしい日本語は、難しい言葉を言い換えるなど相手に配慮したわかりやすい日本語のこと。
外国人への情報発信の手段として、やさしい日本語を広く活用することが期待されています。
ここでは、やさしい日本語がそもそもどのような状況下で作られたのか、その歴史や背景と、やさしい日本語がどんな場面で使われているのか、やさしい日本語を取り巻く環境や自治体の取り組みをわかりやすく解説していきます。
やさしい日本語が作られた背景
やさしい日本語が作られた背景は1995年の阪神・淡路大震災がきっかけでした。
これを機に、外国人に対しても災害時の情報伝達を迅速に行う手段として取り組みが始まり、新潟県中越地震(2004年)、東日本大震災(2011年)を経て、全国に広がっていきました。
普段の日常生活を送る中で外国人へ向けてやさしい日本語で情報発信することも大切です。
こちらは2000年代から地方公共団体や国際交流協会などですでに取り組みが始まっています。

東京都国際交流委員会が2018年に行った「東京都在住外国人向け情報伝達に関するヒアリング調査」では外国人が希望する情報発信言語として、やさしい日本語を選んだ人が76%で最も多く、やさしい日本語に高いニーズがあることが分かります。
やさしい日本語を取り巻く環境や自治体の取り組み
やさしい日本語はさまざまな場面で活用されています。
例えば外国人の児童生徒が通う学校、外国人の労働者が働く企業などが挙げられます。
また、役所から出される文書は難解で意図が読み取りにくいと感じたことはありませんか。日本人でさえもわかりにくいと感じるのですから、外国人にとってはもっと難しいはずです。そのため、国や地方公共団体の窓口ではやさしい日本語を用いた案内が求められています。
現場での活用事例をいくつか紹介していきます。
「一般社団法人やさしいコミュニケーション協会」は医療現場でもやさしい日本語でコミュニケーションをとることを促しサポートしています。医療現場で使われる日本語は専門的で難解なものが多いですが、開かれた医療を提供するためには、国籍を問わず、患者にとって伝わりやすいやさしい日本語を用いたコミュニケーションのほうが望ましいでしょう。
「株式会社セブン-イレブン・ジャパン」は店舗で働くスタッフのうち約10%が外国籍のアルバイトスタッフです。外国人スタッフの初期教育としてはイラスト入りのマニュアルで見せたり、理解が難しい業務についてはeラーニングで説明するなどしてやさしい日本語を活用しています。


やさしい日本語の作り方は?

やさしい日本語の作り方は次の3つのステップで進めます。
- 日本人にわかりやすい文章を作る
- 外国人にわかりやすい文章を作る
- 日本語教師や外国人に確認してもらう
やさしい日本語は誰でも簡単に作れるものではないので、作成した文章を日本語教師に見てもらうなどしたほうがよいでしょう。日本語教師を目指したいという方には日本語の知識を体系的に学べる日本語教師養成講座の受講がおすすめです。
「日本語教師アカデミー」は日本語教師養成講座を一気に検索・資料請求でき大変便利です。日本語教師養成講座をいろいろ見てみたいという方はぜひご活用ください。
それでは以下、日本語の作り方を説明していきます。
日本人にわかりやすい文章を作る
1つ目のステップは「日本人にわかりやすい文章を作る」ことです。
日本人にわかりやすい文章を作るためには以下のようなことを意識します。
日本人にわかりやすい文章が完成したら、外国人にわかりやすい文章を作るステップへ進みます。
外国人にわかりやすい文章を作る
2つ目のステップは「日本人にわかりやすい文章を作る」ことです。
外国人にわかりやすい文章を作るためには以下のようなことに気をつけます。
このほかにも、漢字の量が多すぎないようにしたり、全ての漢字にルビを振ったり、いろいろなことに配慮する必要があります。書き言葉で文章を載せる場合は、外国人がGoogle翻訳などの機械翻訳に頼ることを想定しておいたほうがいいでしょう。ルビを振っていない文章を一緒に載せておけば、コピー&ペーストで文章をそのまま翻訳機にかけて調べることができます。
外国人にわかりやすい文章が完成したら、日本語教師や外国人に伝わるかどうか確認してもらいましょう。確認してもらって問題なく伝わるのであればやさしい日本語が完成したと言えます。
本記事のまとめ
本記事はやさしい日本語が作られた背景、自治体の取り組みなどを中心に解説してきました。
「やさしい日本語」とは難しい言葉を言い換えるなど相手に配慮したわかりやすい日本語のことで、やさしい日本語の作り方で気をつけることは以下の通りです。
- イラスト、写真、図や記号を使ってわかりやすくする
- 回りくどい言い方や不要な繰り返しはしない
- 伝えたいことを整理して情報を取捨選択する
- 3つ以上のことを言うときは箇条書きにする
- 一文に言いたいことは1つだけにする
- 助詞など不足している情報を補う
- 外来語に気をつける
- 「くらい」などの曖昧な表現、「結構です」など複数の意味を持つ表現は使わない
- 文末は「です」「ます」で統一して、尊敬語や謙譲語は使わない
- 漢語、略語、ローマ字、抽象的な言葉をなるだけ使わない
- 「~ないわけではない」など二重否定を使わない
- 受身形や使役表現をできる限り使わない
世界共通語である英語ができればコミュニケーションの幅が広がります。日本語教師の英語力についてはこちらの記事をお読みください。
日本語ボランティアを探している方は、ぜひこちらも合わせてご覧ください。