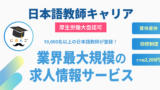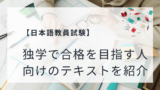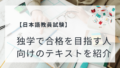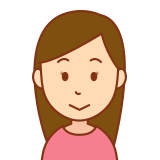
登録日本語教員になりたい!
でも方法がわからない…どうすればいい?
このように、登録日本語教員になりたいという方も多いと思います。
本記事は登録日本語教員について詳しく知りたい方が対象です。
登録日本語教員とは何か、登録日本語教員になるためのルートについて解説していきます。
これから日本語教師を目指す方、日本語教師に転職を考えている方はご一読ください。
登録日本語教員とは?
「登録日本語教員」という名称を初めて聞かれた方も多いと思います。
「登録日本語教員」とは、2023年5月26日の「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律」により制定された、言わば、日本語教師の国家資格です。
この制度は、2024年4月から施行されており(この記事を執筆しているのは2024年10月なので、登録日本語教員制度が始まったのは約半年前)まだ始まって間もないです。
今、あなたが高校生や大学生で「これから日本語教師になりたい」と考えている方は、登録日本語教員になることを強くおすすめします。
なぜなら、登録日本語教員は、政府が認定した「認定日本語教育機関」で働けるからです。
登録日本語教員については、以下の記事で詳しく解説しています。
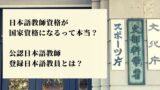
登録日本語教員になるための3つのルートとは?

登録日本語教員になるためのルートは、上図の通りです。
この図を見ていただくと「養成機関ルート」が2つ、「試験ルート」が1つあることが分かります。
以下、それぞれのルートについて、メリット・デメリットを踏まえながらお話していきます。
養成機関ルート:登録実践研修機関と登録日本語教員養成機関の登録を受けた機関の課程を修了
1つ目の「養成機関ルート:登録実践研修機関と登録日本語教員養成機関の登録を受けた機関で課程を修了する方」について解説していきます。
この養成機関ルートの方は、課程修了後、さらに「応用試験」を受ける必要があります。
まず、養成機関には「登録実践研修機関」と「登録日本語教員養成機関」の2つがあることを押さえておきましょう。
登録実践研修機関、登録日本語教員養成機関については、文部科学省のホームページ「登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関の登録等に関すること」に詳細が書かれてあります。
「登録実践研修機関と登録日本語教員養成機関の登録を受けた機関で課程を修了する」という養成機関ルートを経る場合、大学や専門学校で必要な単位を取得しなければなりません。
規定では、大学等は(26単位以上)、専門学校等は(420単位時間以上)となっています。
ご自身が進学を考えている大学、専門学校、あるいは、受講を考えている日本語教師養成講座が、この登録実践研修機関、登録日本語教員養成機関に該当するかどうかを確認しておきましょう。
養成機関ルート:登録日本語教員養成機関の登録を受けた機関の課程を修了
2つ目の「養成機関ルート:登録日本語教員養成機関の登録を受けた機関で課程を修了する方」について解説していきます。
この養成機関ルートの方は、課程修了後、さらに「応用試験」と「登録実践研修機関での実践研修」を受ける必要があります。
また、養成機関ルートは「登録日本語教員養成機関」であることも確認しておきましょう。
先ほどの養成機関ルートと同じく「登録日本語教員養成機関の登録を受けた機関で課程を修了する」という養成機関ルートを経る場合、大学や専門学校で必要な単位を取得することが必要です。
規定では、大学等は(25単位以上)、専門学校等は(375単位時間以上)となっています。
試験ルート
3つ目の「試験ルート」について解説していきます。
試験ルートの方は、「基礎試験」と「応用試験」と「登録実践研修機関での実践研修」を受ける必要があります。
養成機関ルートでは基礎試験が免除になりますが、試験ルートの場合は、基礎試験、応用試験、登録実践研修機関での実践研修、全てを受験しなければなりません。
基礎試験、応用試験は、11月に開催される「日本語教員試験」を受けることになります。
「応用試験」は養成機関ルート、試験ルートでも受験必須です。
以下の記事では「応用試験」について徹底解説しています。

養成機関ルートと試験ルートはどちらがいい?
上記で、養成機関ルート、試験ルートについて詳しく解説してきましたが、それぞれのルートには、もちろんメリットとデメリットがあります。
以下、それぞれのメリット・デメリットについてお話していきます。
養成機関ルートのメリット・デメリット
養成機関ルートのメリットとしては、大学、専門学校、日本語教師養成講座等、該当の養成機関で必要な単位を取得すれば、どなたも必ず修了認定が得られることが挙げられます。
単位を取得するまでが大変ですが、逆に言うと、単位を取得してさえいれば、それ以降は、応用試験に合格すればいいので、試験ルートより楽です。
あなたが養成機関ルートで登録日本語教師を目指すことを考えているのであれば、大学、専門学校、日本語教師養成講座等で、より多くの単位をとっておきましょう。
一方、養成機関ルートのデメリットとしては、費用が高いことです。
大学の学費は国立か私立かによって変わりますが、国立では年間50万円以上かかると言われています。専門学校は学校によりますが、平均すると、年間70万円以上かかるところが多いです。
試験ルートに比べて、養成機関ルートは費用がかかることを覚えておきましょう。
「日本語教師アカデミー」は420時間日本語教師養成講座の資料を無料で一括請求できます。講座をまとめて比較検討したいという方はぜひご利用ください。
試験ルートのメリット・デメリット
試験ルートのメリットとしては、費用がほとんどかからないことです。
先ほど、試験ルートは、基礎試験と応用試験を受験する必要があるとお話しましたが、基礎試験と応用試験の受験料は合わせて18,900円です。
基礎試験や応用試験に独学で挑んでみようと考えているなら、日本語教師試験の用語集やガイドブックなどの「日本語教師試験の対策本」を使うことをおすすめします。
一方、試験ルートのデメリットとしては、日本語教員試験に合格しない限り、登録日本語教員にはなれないということです。
日本語教員試験の難易度は、基礎試験が総合得点で8割、応用試験が総合得点で6割となっており、合格するには高いスコアが求められます(「令和6年度 日本語教員試験 試験案内」には、年度ごとの難易度差等により合格基準の調整を行うことがあるとの記載があります)。
時間と費用はかかるけれど、確実路線でいくなら「養成機関ルート」を、日本語教員試験(基礎試験、応用試験)に合格できない限りは登録日本語教員にはなれないけれど、費用を抑えたいなら「試験ルート」を選びましょう。
日本語教員試験に独学で臨みたい方には、こちらの記事で紹介している書籍が役に立ちます。
本記事のまとめ
いかがでしたか。
本記事は「登録日本語教員試験になるための方法」について解説してきました。
「登録日本語教員」「登録日本語教員になるためのルート」「養成機関ルートと試験ルートのメリット・デメリット」は以下の通りです。
- 登録日本語教員:2023年5月「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律」で制定された日本語教師の国家資格。2024年4月施行。
- 養成機関ルート:登録実践研修機関と登録日本語教員養成機関の登録を受けた機関の課程を修了する ※養成課程修了後、「応用試験」を受ける必要がある
- 養成機関ルート:登録日本語教員養成機関の登録を受けた機関の課程を修了する
※課程修了後、「応用試験」と「登録実践研修機関での実践研修」を受ける必要がある - 試験ルート ※基礎試験、応用試験、登録実践研修機関での実践研修を受ける必要がある
- 養成機関ルート
メリット😊⇒大学、専門学校、日本語教師養成講座等、該当の養成機関で必要な単位を取得すれば、必ず修了認定が受けられる
デメリット😢⇒費用が高い - 試験ルート
メリット😊⇒費用はほとんどかからない
デメリット😢⇒日本語教員試験に合格しない限り、登録日本語教員にはなれない
養成機関ルート、試験ルートはそれぞれ一長一短です。
登録日本語教員になるにはどのルートがいいか、ご自身に合う方法を選んでみてくださいね。
また、「日本語教師キャリア」では、日本語教師の就職・転職を支援しています。
登録日本語教員への移行にかかる資格取得支援などが福利厚生として受けられる日本語学校の求人も多数扱っています。
日本語教師を目指す方、これから登録日本語教員試験を受けられる現役日本語教師の方は、ぜひこの機会に登録してみてください。
☟ 「日本語教師キャリア」に登録する ☟